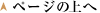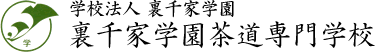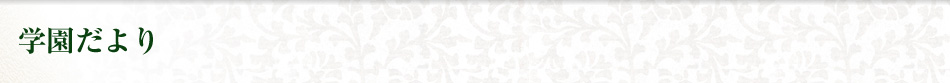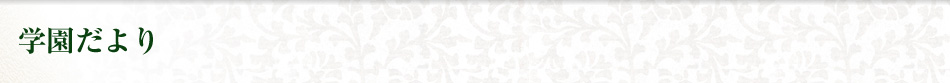
学園歳時記【かんなづき第1号】〜雲無心
平成27年10月06日(火)

10月6日(火)、石清水八幡宮(八幡市)にて坐忘斎家元奉仕による献茶式が執り行われました。
石清水の献茶式では例年、茶道科3年生が添釜を担当させていただいています。裏千家学園がまだ茶道研修所だった頃、7期生から始まった慣例です。
以来、学園生にとって学外で喫客をもてなす貴重な機会となっています。
今回3年生(52期)は茶席の主題を初心とし、入学して初めに覚えた盆略を点前に選びました。

床は坐忘斎家元筆の短冊『雲無心』。悠々と流れる雲のように、自分たちらしくありのままの姿で茶席に臨みたいという思いに重なります。
鵬雲斎大宗匠好みのツボツボ籠にツルウメモドキとオケラ。点前座の背景に藍色の空が広がり、銀色に光る十三夜の月が浮かんでいます。
舞台手前には野にあるような自然な姿で芒が添えられ、秋の夜長を演出します。

小ぶりな面取風炉に十二代寒雉作の鉄瓶。玄々斎宗匠の文字が鋳込まれています。茶杓は井口海仙宗匠作、銘は「らしく」。
大棗の秋草と即全作の色絵茶碗は石清水八幡宮を抱く男山山頂にふさわしい景色。
スペイン・グラナダ地方で作られた寄木細工の民芸品が盆に見立てられました。
幾何学的な八角形の模様は52期生8人が手を携えた姿を象徴しているようです。

手作りの栗きんとんの銘は『もも栗三年』。茶道科3年間の実りが表現されています。
茶席の記念になり、実際に使えるものをお客様にお渡ししたいとの思いから席札を千鳥板にしました。
富士・千鳥・鯛の三種の焼き印が押された特注の品です。
自然豊かな男山の地に月見風情を織り交ぜた52期生による等身大の野点席。澄んだ秋空のもと、およそ200名の喫客をもてなしました。