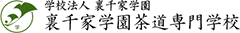五大明王の引越し
平成26年06月11日(水)

6月11日(水)、茶道科3年生は醍醐寺(伏見区)へハイキングに出かけました。醍醐寺は真言宗醍醐派の総本山。空海の孫弟子である理源大師・聖宝(しょうぼう)によって874年に創建されました。開山堂などが点在する山頂部は上醍醐、五つの山内寺院からなる山裾は下醍醐と称されます。合わせて200万坪を越える広大な敷地に国宝・重文指定の建造物や文化財数万点を有しています。歴史的・文化的価値が高く評価され平成6年に世界文化遺産に登録されました。

登山口には成身院と名付けられた御堂。通称「女人堂」です。かつて上醍醐が女人禁制だったころ、女性はここから山頂を拝んでいたとされています。竹の杖を携え山登り開始。前日の雨のせいで山道はところどころぬかるんでいます。急勾配の坂道と果てしなく続く階段が体力と水分を奪いとります。休憩を挟みながら慎重に歩を進めました。
登りはじめて1時間が経過。最後の難所、つづら折りの坂道に差しかかったとき、箪笥ふた棹ほどの大きな荷物とすれ違いました。揃いのポロシャツを着た男性が10人がかりで慎重に運び下ろしています。

恐るおそる訊ねると箱の中身は何と不動明王の台座でした。7月19日から奈良国立博物館にて開催される特別展覧(『醍醐寺のすべて』)のため、五大明王すべてが移送されるとのこと。五大明王といえば、毎年2月23日に五大堂で執り行われる醍醐寺最大の行事、「五大力さん」が有名です。「五大力尊御影」の御札は、あらゆる災難を払い除けてくれるご本尊の分身。学園の玄関先にも掲げられています。
五大堂では中央の不動明王がすでに梱包を終えたばかり。軍荼利(ぐんだり)明王の光背を箱に収める作業の最中でした。現場の指揮を執る学芸員の方から五大明王の由来や特徴について伺うことができました。

上醍醐では五大堂をはじめ、国宝の薬師堂や如意輪堂を拝観し、開山堂前の見晴しのよい広場で昼食休憩をとりました。目の前に巨椋池干拓地が広がり、その向うに男山と天王山が見渡せます。
醍醐寺発祥の地である醍醐水の霊水をいただきリフレッシュした後、下醍醐を目指して下山しました。醍醐道沿いの南門から境内に入り、仁王門や金堂、国宝の五重塔を拝観しました。

京都市内には珍しく、度重なる戦乱・大火による倒壊を免れた古い建造物を醍醐寺は多く遺しています。国宝文化財の鑑賞に加え、ご本尊の引越という珍しい光景を目の当たりにした今回のハイキング。水屋当番を司る3年生がお参りしたおかげで、下半期の裏千家学園も安泰隆昌となることでしょう。