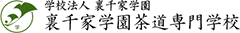学園だよりアーカイブ
石灯籠を見極める
平成26年10月28日(火)
「昔の茶人たちが茶庭の景色としての石灯籠にこだわった理由が少しわかりました」と茶道科3年生の談。

朝の空気がひんやり感じられるようになりました。炉開きはもう目の前です。10月28日(火)の午後、「庭園」講義(尼崎博正先生)で茶道科2・3年生が北白川の西村石灯呂店を訪ねました。比叡山麓は古くから良質な黒雲母花崗岩、いわゆる白川石が採れた土地。平安時代からすでに採石や石塔製作が盛んに行われていました。鎌倉時代には仏教が隆盛を極め、石工技術も高度に発達。桃山時代になると茶の湯の影響を大きく受け、その技術と表現がいっそう洗練されていきました。
西村石灯呂店の西村金造氏・大造氏親子は石工芸の第一人者。京都迎賓館の建設にあたり石造全般を手がけられています。手彫りのみの伝統的な工法を受け継ぐ五代目の金造氏は昭和59年に、当主である長男の大造氏は平成7年に伝統工芸士に認定されました。西村石灯呂店はまた、1950年代に彫刻家のイサム・ノグチが通った工房としても知られています。

今回の講義では石灯籠や宝塔の種類と特徴、製作時代を判別するポイントを尼崎先生から学びました。また、工房で六角形の基礎となる石をノミではつる作業を間近で拝見させていただきました。学生からは「さまざまな灯籠のなかに鎌倉時代に造られたものもありました。度重なる戦火や自然災害を免れ、時代を越えて佇む姿が大変貴重なものに感じられました」、「石を間近で見て、じっさいに触って白川石の特徴がよくわかりました。製作時代を見極めるツボを教わり、庭園を鑑賞する楽しみがまた一つ増えました」と感想が聞かれました。