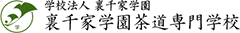観月茶会
平成30年09月15日(土)
京都市内の大学・高等学校の茶道部員や指導にあたられる先生など、およそ140名をお招きして観月茶会を催しました。茶道科生が席主を務め、案内やお運びなどには1年コースの生徒も加わり、研究科・外国人研修コースは客に招かれました。

待合に案内されると、学園に在籍する中国・台湾・ベトナムからの留学生がそれぞれ準備した自国の中秋の名月に用いるランタンが飾られ異国情緒を演出します。床には嫁入り道具の一つという食籠に三種の月餅が用意されていました。

本席の掛物は李白の詩、「雲想衣裳花想容…」と中国の中秋節の物語に登場する仙女「嫦娥」が描かれています。半東から月にまつわる神話「嫦娥奔月」を聞きながら長板二つ置きの点前は進みます。
昔々、嫦娥という美しい女性がいました。ある時、嫦娥は強盗に遭ってしまいます。命を永らえるため、夫が大事にしている西王母から貰い受けた不老不死の仙薬を飲んだところ、月に昇って仙女となりますが、一人寂しく暮らすことになりました。言い伝えでは、夫が彼女を偲んで供えたのが月餅だと言われています。また一説には、夫から仙薬を盗んで月に逃げたため、罰としてヒキガエルの姿に変えられたしまったとも言われています。(中国では月に浮かぶ模様はウサギではなくヒキガエルと言われているそうです)
そして試作を重ねた手作りの菓子は、赤と白の餡玉を寒天で固めたもので、赤玉は仙薬、白玉は水に映る満月を表しています。


点心席は秋をたっぷり感じられる食材でした。

三階のお楽しみ席では鶴首茶入、唐犬釜など生き物に因んだ道具の名称に関するクイズや、茶カブキに倣って二種の濃茶の聞き茶を楽しんでいただきました。また、「和歌を詠む」の授業で月に因み詠んだ歌を夫々が短冊に仕上げ、それを展示しましたが、優秀作品1点を授業担当の八木意知男先生に選んでいただきました。

〈主な道具〉
床 清平調詩(一) 嫦娥奔月図
花 白芙蓉
花入 唐銅象耳
香合 菊置上蛤
釜 霰
風炉 朝鮮
水指 色絵祥瑞五節句
薄器 秋の野蒔絵
茶杓 銘 秋の夜
茶碗 楽 兎の図
〈点心〉
杉板盛込み 飯 ひさご物相型 きのこ飯
万願寺唐辛子とししとうの胡麻油炒め
薩摩芋の甘露煮
香の物
椀 刻みレンコン入り真薯、菊菜を添えて